G検定は、AIの基礎知識や用語、活用事例を幅広く理解していることを証明する資格で、E資格は、深層学習の理論・数学・実装スキルを総合的に問う高度なAIエンジニア向け資格です。
どちらも人工知能(AI)に関する知識を測定するための日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する資格試験です。
G検定は、AIの基礎知識や歴史、用語、活用事例、倫理などを幅広く理解していることを証明する資格で、E資格は、深層学習の理論や数学的基礎、実装スキルを備えたAIエンジニアであることを証明する資格です。
ここでは、そんな有名なAI資格である「G検定」と「E検定」の違いや難易度について詳しく解説し、G検定の対策方法などについても紹介していきます。
- G検定とE検定の難易度や試験内容などの違いを知りたい
- G検定について内容や対策方法など詳しく知りたい
- E検定について内容や対策方法など詳しく知りたい
- これからG検定を受験する

G検定(ジェネラリスト検定)とE検定(エンジニア検定)は、いずれも日本ディープラーニング協会(JDLA)が提供しているAI関連の資格試験ですが、それぞれの目的、対象者、内容、そして難易度が異なります。
g検定とe検定の違いや内容を比較!
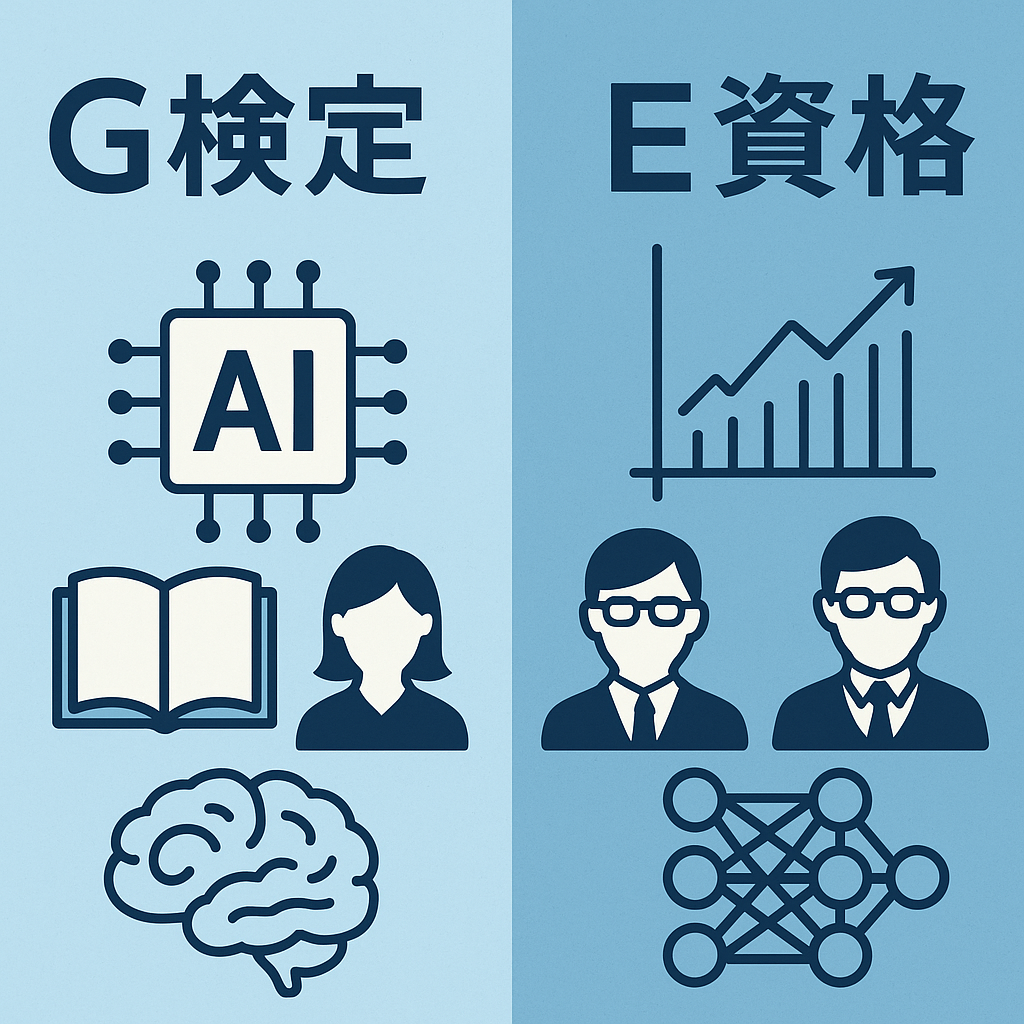
| 特徴 | G検定 | E検定 |
|---|---|---|
| 目的 | AIの基礎知識とビジネス活用の理解 | AI技術を実装・開発できるエンジニア育成 |
| 対象者 | ビジネスパーソン、AIに関心のある初心者 | AIエンジニア、開発者 |
| 内容 | AIの基礎、法規制、適用事例 | 深層学習、アルゴリズム、プログラミング |
| 試験形式 | 選択式(オンライン) | 数式、プログラミング問題、選択式 |
| 合格率 | 75%前後 | 60~70% |
| 難易度 | 初心者向け | 中〜上級者向け |
G検定とE検定の違いや難易度について詳しく解説します。
そもそもg検定とは?試験の概要
- ①目的: G検定はAI、特にディープラーニングに関連する知識を基礎から幅広く理解し、活用できる能力を確認する試験です。特に、エンジニアとしての技術力よりも、AIに関する知識を社会的、ビジネス的にどう活かすかを問われます。
- ②形式: CBT(コンピュータベーステスト)方式で、120分間に約200問の問題に解答します。内容は選択肢問題が中心です。
- ③内容:AIの歴史や倫理、ディープラーニングの基礎、具体的なアルゴリズム、AI技術が社会やビジネスに与える影響まで幅広い知識が問われる
- ④合格率: 合格率はおおむね70~80%前後ですが、過去のデータに基づくため、年ごとに変動することがあります。
G検定(ジェネラリスト検定)とは、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、人工知能やディープラーニングに関する基礎知識を問う検定試験です。
正式名称は「JDLA Deep Learning for GENERAL」といい、主にAIを活用・理解する側の人材を対象としています。
この資格は、AI技術を「開発する人」ではなく、「活用する人」向けに設計されています。
この検定は、AIプロジェクトにおける企画や意思決定に関わるビジネス職、管理職、非エンジニアの方々を主な受験者と想定しており、ディープラーニングを含むAI技術の基礎的な仕組みや活用方法を理解できるかが問われます。
出題内容は、AIの歴史や機械学習の基本、ニューラルネットワークの仕組み、さらにAI倫理や法的な論点、ビジネス活用事例など多岐にわたります。
試験は年に数回、オンラインで実施され、自宅のPCから受験可能です。プログラミングスキルは必要なく、文系出身者でも挑戦しやすい検定として人気があります。
難易度は比較的取り組みやすいレベルとされており、AIの導入や運用に関心がある人、AI関連のプロジェクトに関わる人にとって、G検定は信頼性のある入門的な資格といえるでしょう。
E検定(エンジニア検定)とは?試験の概要や問われる内容
- ①【目的】AI技術を実際に開発・実装できるエンジニアのスキルを評価する試験で、実務でAIモデルを開発・応用できるエンジニアを育成することが目標
- ②【対象者】機械学習や深層学習の技術を実務に応用したいエンジニアや、AI開発に携わる人々が主な対象です。
- ③【内容】深層学習のアルゴリズム、モデル設計、最適化手法、データ前処理、評価手法など、技術的な知識が中心です。
- ④【難易度】AI技術の深い理解と実践力が求められるため、難易度は高く、プログラミングスキルや数学的な知識が必要となります。
E資格(エンジニア資格)は、同じく日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する試験で、正式名称は「JDLA Deep Learning for ENGINEER」です。
この資格は、実際にディープラーニングを使ってAIを開発・実装するエンジニア向けに設計されたものであり、より専門的かつ技術的な内容が問われます。
E資格の大きな特徴は、受験するためにはJDLAが認定する講座(JDLA認定プログラム)を修了していなければならないという点です。
これにより、ある一定以上の知識とスキルを持つ人だけが受験できる仕組みとなっています。
試験内容には、線形代数や微分積分、確率統計といった数学の知識から、機械学習・深層学習のアルゴリズム、さらに畳み込みニューラルネットワーク(CNN)や再帰型ニューラルネットワーク(RNN)、最適化手法、Pythonによる実装方法などが含まれます。
試験は指定された会場でCBT方式(コンピュータベーステスト)により行われます。
E資格は、AIを自ら設計・構築する能力を客観的に証明できる資格として、エンジニアやデータサイエンティスト志望の人にとって非常に有用です。
高度な知識とスキルが求められるため、難易度は高めですが、その分業界からの評価も高いのが特徴です。
g検定とe検定の難易度の違いは?どっちが難しい?
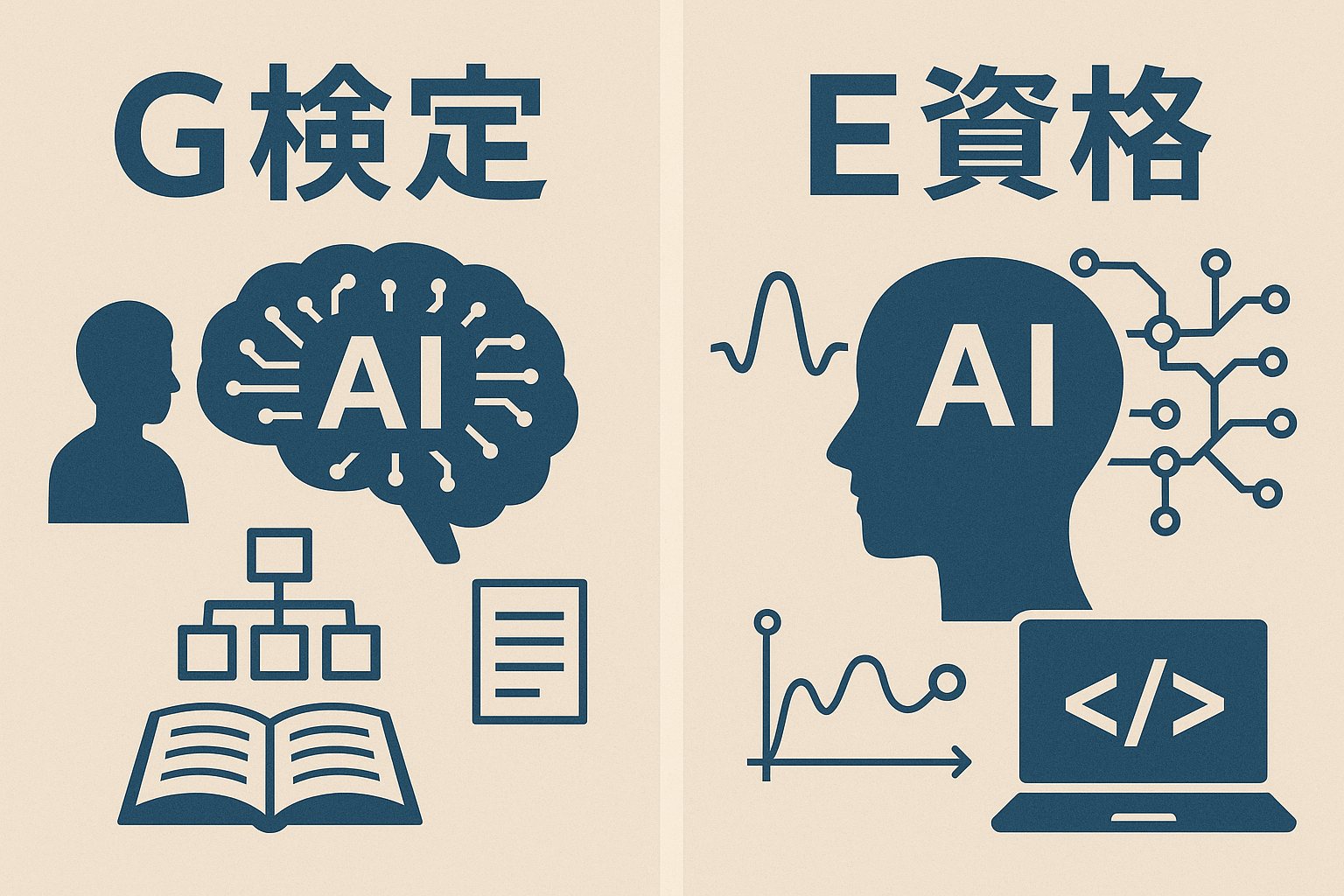
G検定の難易度
G検定は初学者やビジネスパーソンでも取り組みやすい試験で、特にAIの技術的な背景やプログラミングに不安がある人でも合格可能です。
G検定は、AIの歴史・用語・倫理・応用事例などを幅広く問う知識試験で、数学は高校レベル程度、プログラミング経験も不要です。
暗記と理解が中心で、初学者でも30時間~50時間の学習で合格を目指せます。
難易度は比較的易しめで、AIの基礎知識を習得することに重点が置かれています。
E検定の難易度
E検定は、技術的な深さが求められるため、エンジニアやAI開発者向けであり、難易度は高いです。
合格率は60~70%程度ですが、受験者の中にはかなりの実務経験者が含まれており、また、JDLA認定プログラムの受講も必須条件なので、G検定より難易度が高いと考えられます。
理論的な問題だけでなく、実際のプログラミングや数式を使った問題も出題され、特に深層学習や数学、プログラミングに精通していないと合格は難しいです。
プログラムやアルゴリズムに関する実践的なスキルが求められるため、準備に時間がかかる可能性が高いです。
結局どっちが難しい?
ざっくり言うと、E資格の方が圧倒的に難しいです。
理由と背景を整理するとこうなります。
| 項目 | G検定(ジェネラリスト検定) | E資格(エンジニア資格) |
|---|---|---|
| 主な内容 | AIの基礎知識・歴史・用語・倫理・法律・応用事例など | 深層学習の理論・数理(線形代数・確率統計・微分積分)・ニューラルネットワーク構造・実装 |
| 出題形式 | 選択式(マークシート形式) | 選択式(ほぼ全問応用計算問題) |
| 数学レベル | 高校~大学初年レベルの基礎理解があれば可 | 大学理工学部レベルの数理+実装経験が必要 |
| 実務スキル要求 | 不要(知識中心) | 必要(Pythonや深層学習フレームワークの経験) |
| 受験資格 | 誰でも受験可 | JDLA認定プログラム修了が必須 |
| 合格率 | 約70〜80% | 約60~70%前後(時期により変動) |
| 勉強期間の目安 | 社会人で1〜2ヶ月 | 社会人で3〜6ヶ月以上(実務経験あれば短縮可) |
- 基礎知識中心 → G検定:暗記+理解が中心で、未経験者でも時間をかければ合格可能。
- 理論と実装中心 → E資格:数理やコードが必須で、AIエンジニアを想定した内容。数学やプログラミングに不慣れだとかなりハード。
つまり、
- AIの全体像や用語を学ぶならG検定
- 深層学習を理論から実装まで理解するならE資格(難度高)
g検定の難易度は?難しいと感じる理由!

g検定の難易度は、AI資格の中では比較的易しめですが、ITパスポートよりも難易度は高いと言われています。
g検定の合格率は7~8割ほどで、それほど難しい試験ではないことが分かります。
ただし、g検定ではAIやディープラーニングに関する幅広い知識が問われるので、しっかりと対策をしていかないと合格することは難しいでしょう。
G検定が難しいと感じる理由には、主に以下のようなことが挙げられます。
①知識量の多さ
AIやディープラーニングに関する知識は、技術的な内容だけでなく、歴史や倫理、実際のビジネス応用例など幅広い分野にわたります。
そのため、初心者にとっては、覚えるべきことが多く感じられます。
特に、AIの理論や数式の部分は、技術的なバックグラウンドがないと理解に時間がかかる場合があります。
②時間の制約
試験は120分で200問前後の問題を解くため、時間配分が非常に重要です。
問題自体は短い選択肢問題が多いものの、1問1問の理解が必要です。(長い文章問題もあります)
また、かなりの分量があるため、知識を効率的に整理し、スピーディーに解答する訓練が必要です。
③技術的な理解
技術者でなくても受験できる試験ですが、ディープラーニングや機械学習の基本的なアルゴリズムについての理解は不可欠です。
特に、ニューラルネットワークや勾配降下法などの具体的なアルゴリズムについての知識が問われます。
これらの内容は、数学やプログラミングの基礎がない場合、理解するのに時間がかかる可能性があります。
④最新技術の追跡
最後に、AIの分野は進化が速く、新しい技術や研究が次々と発表されるので、最新の情報もカバーする必要があります。
最新の技術についても問われることがあるので、AI関連のニュースや新しい情報にも目を向けておきましょう。
試験対策としては、基本的な理論に加えて、最新の技術動向やトレンドも抑えておく必要があるため、常に新しい情報にアンテナを張っておくことが重要です。
g検定対策のコツ
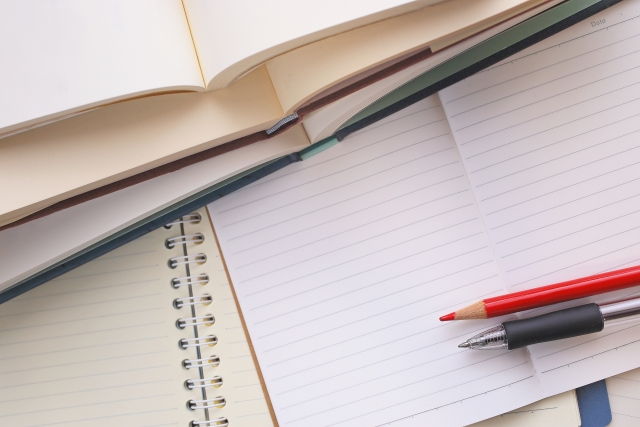
G検定は、しっかりと対策をすれば合格可能な試験です。以下のポイントを意識して勉強することが大切です。
①問題を解くことに慣れる
G検定では、問題を解くのに慣れることが非常に有効です。
G検定は120分で220問に回答しなくてはならないため、時間との闘いでもあります。
G検定は過去問が公開されていないため、参考書等に掲載されている演習問題などを解いて、問題を解くのに慣れておくことが重要です。
出題される問題は、定番のテーマが多く繰り返し出題されるため、過去問をしっかり解いて、どの部分が頻出なのかを理解しておくことが合格の近道です。
②とにかく用語を覚える
次に、とにかく用語を覚えることが重要です。
G検定は問われる知識量が多いため、多くの用語を覚えておく必要があります。
長期間かけてダラダラ勉強するよりも、短期間に集中して取り組むほうが効率的なので、試験までの1〜2か月間を集中的な勉強期間とし、繰り返し問題を解くことで知識の定着を図りましょう。
③参考書の活用【公式シラバスがおすすめ】
続いて、参考書を活用するのがおすすめです。
「AI白書」や「ディープラーニングG検定公式テキスト」といった定番の参考書をしっかり読み込むことが基本です。
特に、AIの歴史や倫理の部分は参考書で体系的に学ぶことが重要です。
④オンライン学習ツールを活用する
また、書籍だけでなく、オンラインの学習ツールを活用するのもおすすめです。
Udemyの講座やYouTubeなど、AIや機械学習に関するオンライン講座を活用するのも一つの手です。
特に、初心者向けの解説動画は視覚的に理解しやすく、難解なアルゴリズムや数学的な概念もわかりやすく解説されています。
また、隙間時間などに無料・有料アプリで学習するのも良いと思います。
⑤AIの実践事例も把握する
技術的な理解だけでなく、AIの実際のビジネス応用例や最新の研究についても押さえておく必要があります。
これにより、単なる技術知識だけでなく、AIがどのように実社会で活用されているのかを深く理解できます。
参考書等で技術的な理解だけでなく派生知識までよく確認しておきましょう。
g検定を受けてみた感想【おまけ】

受験者からは、次のような声がよく聞かれます。
- 「知識量が膨大で、しっかりと準備をしておかないと難しい。」 → 幅広い範囲から出題されるため、体系的に勉強することが重要。
- 「ディープラーニングやニューラルネットワークなど技術的な部分は理解に時間がかかったが、参考書が役立った。」 → 数学的な基礎が必要な箇所は、丁寧に時間をかけて学ぶ必要があります。
- 「時間配分が難しい。問題数が多く、時間が足りなくなることが多かった。」 → スピードを意識した問題解きの練習が不可欠です。
それでは最後に、筆者がg検定を受けてみた感想を述べて終わろうと思います。
g検定は問題の難易度自体はさほど難しくはなかったのですが、やはり問われる知識量が多く、悩んだ問題も少なくありませんでした。
g検定に合格するためにはしっかりと用語の意味を理解し、過去問演習などでアウトプットしながら網羅的に学習する必要があります。
ただ、範囲が広いので要点を抑えることも大事で、特にディープラーニングや機械学習に深く関連する用語などは抜け漏れのないようにしましょう。
ちなみに、筆者も使っていた個人的におすすめテキストは、「G検定公式テキスト」です。
まとめ
G検定は、AI技術やディープラーニングに関する知識を幅広く理解し、その応用力を証明する試験です。
難易度は決して簡単ではありませんが、体系的に学び、過去問や参考書を活用すれば、技術職でなくても合格が可能です。
特にAI技術をビジネスに活かしたいと考えている人にとっては、非常に価値のある資格といえます。
最後までご精読いただきありがとうございました。


コメント